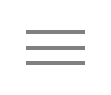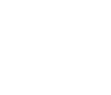ニュース
2024.12.05
【第12回浜松国際ピアノコンクール】第2位ヨナス・アウミラー氏に聴く
静岡県は浜松市にて、11月8日から25日に開催されていた浜松国際ピアノコンクール。3年に1回開催されてきた当コンクールは2021年に予定されていた第11回がコロナ禍の影響で中止となり、6年ぶりの開催となりました。
この度見事第2位を獲得したヨナス・アウミラー氏が河合楽器本社・竜洋工場に訪問してくださった際にインタビューに応えてくださいました!

演奏動画
■曲目
| ラウンド | 演奏日 | 演奏曲目 |
|---|---|---|
| 第1次予選 | 11月11日 | – J. S. バッハ/F. ブゾーニ 前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532 – A. スクリャービン 練習曲 嬰ハ短調 Op.42-5 – S. ラフマニノフ 絵画的練習曲 ハ短調 Op.39-1 |
| 第2次予選 | 11月16日 | – F. ショパン 舟歌 嬰ヘ長調 Op.60 – R. シューマン プレスト・パッショナート Op.22 – C. ドビュッシー 前奏曲 第2集 より「交代する3度」 – C. ドビュッシー 前奏曲 第2集 より「花火」 – A. スクリャービン 幻想曲 ロ短調 Op.28 – 猿谷紀郎: Division 28 for Piano |
| 第3次予選 | 11月20日 | – W. A. モーツァルト: ピアノ四重奏曲 第2番 変ホ長調 K.493 – J. S. バッハ トッカータ ト短調 BWV915 – F. リスト 「伝説」より 波を渉るパオラの聖フランチェスコ S.175-2 – L. v. ベートーヴェン ピアノ・ソナタ 第32番 ハ短調 Op.111 |
| 本選 | 11月23日 | – J. ブラームスピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 Op.15 |
■演奏動画(ファイナル)
■インタビュー
コンクール期間中について
――― 第2位おめでとうございます。そしてカワイに来てくださりありがとうございます!コンクールについての感想を教えていただけますか?
浜松国際ピアノコンクールは非常によくオーガナイズされていると感じました。浜松への移動、ホテルでの滞在、練習室の手配、必要な場所や時間の案内など、すべてがスムーズでした。
参加者として、とても丁寧にケアしていただけたおかげで、音楽や練習、ステージでのパフォーマンスに集中することができました。
―――今回のホールでの演奏について教えてください。音の響きや、パフォーマンスについて。
演奏者として自分の音を客席で聞くことはできないので、正確にはわかりません。ただ、非常に良いホールであり、音響も素晴らしかったと感じました。
特に印象的だったのは、大久保さん(カワイの調律師)がメインホールの音響に合わせてピアノの調律や音色を再調整してくれたことです。これがなければ、演奏を変えて対応する必要があったかもしれません。彼のサポートのおかげで、ステージ上での演奏を心から楽しむことができました。
―――ホールの変更とともに、演奏スタイルも少し変更されたのでしょうか?
小ホールよりメインホールの音響は少し曖昧でクリアさに欠けると感じたので、少し音量を上げて演奏しました。とはいえ、大久保さんがピアノを調整してくれたおかげで、安心して演奏することができました。
―――他の参加者との交流について教えてください。印象的な出来事や、影響を受けたことはありましたか?
実は以前から既に多くの参加者を知っていました。昨年スイスのルツェルン・フェスティバルで出会った友人とは、同じフライトでミュンヘンから東京へ来て、さらに一緒に新幹線で浜松へ向かいました。コンクールでは同世代の人たちとよく顔を合わせるので、自然と親しくなります。今回は一緒にランチやディナーをしたり、時にはビールを飲んだりと、和やかで楽しい時間を過ごしました。
ピアニストは練習室で一人で過ごすことが多いので、他の参加者と経験を共有できることは、とてもありがたいことです。

演奏について
―――今回のコンクールで演奏する曲目はどのようにして選択したのでしょう?
先生と一緒に選びました。私が提案したレパートリーに対し、「これはやめたほうがいい」「こっちのほうが良い」とアドバイスを受けて変更した形です。
私としては、音楽家としての自分の多様な一面を表現したかったので、さまざまな時代や作曲家の作品を含めるよう心がけました。
ファイナルラウンドでは、すでにオーケストラと演奏経験のあるピアノ協奏曲を選びました。限られた準備時間と少ないリハーサルを考えると、慣れた曲を選ぶのが最善だと思いました。
―――曲目の最終決定はいつでしたか?
確か8月で、最終プログラムを提出したのは締切日の当日でした。
―――本大会ではYouTube配信もされていました。自分の演奏を録音やライブ配信で振り返ることはありますか?
はい、いくつか聴き返しました。ステージ上での感覚と、録音やライブ配信での音の印象は異なるので興味深かったです。ただ、実際にホールで聴いた感覚とはまた違うので、録音は全体の一部しか伝えられないとは思います。
―――演奏前の決まったルーティンなどはあるのでしょうか?
決まったルーティンは無いのですが、今回浜松では面白いルーティンができました。演奏順が、午後や夕方になる事が多かった為、うなぎを食べてから臨むようにしていました。重すぎず、軽すぎず、かつエネルギーになって眠くならない…とても適切な食べ物を見つけました。唯一ファイナルの演奏が11時だったので直前に食べられなかったのが残念でした(笑)。

SK-EXについて
―――今回のコンクールでもSK-EXを選ばれましたね。仙台国際ピアノコンクールや、カワイ表参道での演奏など、これまでのキャリアでも繋がりがあると思いますが、その魅力を教えてください。
SKを選んだ理由はいくつかありますが、一番大きいのは音の持続性です。他のコンサートピアノと比べて、SK-EXは音が非常に長く響きます。この「音の長さ」はピアニストが直接コントロールできない部分ですが、楽器がそれを提供してくれると、より多くの表現の可能性が広がります。
また、ダイナミクスの幅広さも魅力的です。非常に繊細で静かな音から、オーケストラと共演する際の力強い音まで、どんな場面でも対応できます。そして、何より私の演奏スタイルと非常に合っていると感じます。鍵盤のバランスも良く、思い通りの演奏ができる楽器です。
もちろんこれまで演奏したことはありますが、仙台と浜松のホールでは規模が異なるので、ピアノもそれに合わせた特性を持っていました。どちらも素晴らしい楽器でした。
これからの目標
―――以前は、ピアノ編曲に大変意欲的だと仰っていましたね。今後の目標や計画について教えてください。
これまでいくつかの編曲を手がけてきましたが、さらに新しいピアノ編曲に挑戦したいと考えています。一台のピアノだけでなく、二台ピアノ用の編曲にも興味があります。昨年作った二台ピアノの編曲は、5月にクリーブランドで友人と初演しました。この経験から、さらに新しい作品に挑戦したいと思っています。
また、アメリカでの学業を終えたので、これからはヨーロッパでのコンサート活動を増やしたいです。現在はミュンヘンを拠点にしていますが、ヨーロッパ全体が好きです。ヨーロッパのどの地でも演奏できることを楽しみにしています。
ヨナスさんの豊かな音楽人生と、ピアノへの深い愛情を感じるインタビューとなりました。彼の未来の活躍にも注目です!
プロフィール
ヨナス・アウミラー(Jonas AUMILLER)
ドイツ出身。2021年ヨハネス・ブラームス国際コンクール(ドイツ、デトモルト)優勝。2022年第8回仙台国際音楽コンクール第2位及び聴衆賞受賞。その他、2022年ニューヨークヴァンドーム賞、2018年エトリンゲン国際青少年ピアノコンクール(ドイツ)、The Premio Roberto Melini(イタリア、バゼルガ・ディ・ピネ)、Piano Talents(イタリア、ミラノ)、ロベルト・シューマン国際青少年コンクール(ドイツ、ツヴィッカウ)など多数のコンクールで入賞している。
ヨアヒム・ガウク前ドイツ大統領に招かれベルリンのベルビュー宮殿(大統領官邸)で演奏。また、ドイツの有名なコンサートシリーズである『Winners and Masters in Munich』、シュレスヴィヒ・ホルシュタイン音楽祭、イタリアの国際音楽アカデミー、イタリア・モーツァルト財団、ニューヨークのサミット音楽祭などでリサイタルを行う。
1998年ミュンヘンで生まれ、7歳よりピアノを始める。F.A. Bonporti音楽院(イタリア、トレント)においてマッシミリアーノ・マイノルフィの指導のもと、音楽学士号「summa cum laude(最優等)」を取得。2018年より、世界的なピアニストであり教育者であるセルゲイ・ババヤンのもとで、ニューヨークのジュリアード音楽院および、現在はクリーヴランド音楽院で学び、2022年に修士号とともに優れた業績に対するアーサー・レッサー記念賞を受賞。2022年8月からは、全額奨学金を得てアーティスト・ディプロマを取得し、現在もクリーヴランド音楽院においてババヤン先生の元で学ぶ。
19世紀と20世紀のピアニスティックな伝統をこよなく愛し、オーケストラやオルガンの作品をピアノ用に編曲し、定期的にリサイタルで演奏している。
■Shigeru Kawaiフルコンサートピアノ 『SK-EX』について
「世界一のピアノづくり」を目指す当社が、2001年に発表したフルコンサートピアノのフラッグシップモデル。コンサートピアノとして要求される最高の表現力を実現するために、響板には十分に厳選した材料だけを使用し、原器工程と呼ぶ伝統的な手作り工程で生産。またShigeru Kawaiグランドピアノシリーズで採用した新素材を随所に取り入れた革新的なウルトラ・レスポンシブ・アクションIIが、高い連打性と安定したタッチ感を提供する。繊細で伸びやかなピアニッシモに加えて、力強く輪郭のはっきりした響きが特長。