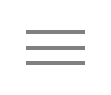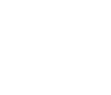ニュース
2025.04.25
【レビュー編】ロン=ティボー国際ピアノコンクール2025
3月25日から30日にかけて、フランス・パリで開催されたロン=ティボー国際コンクール。今年も世界中から注目を集めるこの伝統ある音楽コンクールに、多くの若き才能が集い、白熱した演奏が繰り広げられました。
本記事では、現地で取材を行った「ピアニスト/国際ピアノコンクール・リポーター」のアーリンク明美さんによるファイナルのレビューをお届けします。臨場感あふれる現地の空気感とともに、各出場者の演奏内容や審査の傾向など、見どころ満載の内容となっています。
今回はレビュー編。後日公開予定のインタビュー記事とあわせて、ぜひお楽しみください。
20世紀前半のフランスの偉大なアーティスト、ピアニストのマルグリット・ロンとヴァイオリニストのジャック・ティボーによって、80年以上前の1943年に創設された「ロン=ティボー国際コンク―ル」のピアノ部門が3月25日から30日に渡ってフランスのパリで開催され、17歳のキム・セヒョンさん (韓国)が優勝、日本の神原雅治さんは4位入賞という結果で幕を閉じた。
第1位 キム・セヒョン Saehyun Kim(17歳 / 韓国)
第3位 イ・ヒョ Hyo Lee(17歳 / 韓国)
第4位 神原雅治 Masaharu Kambara(21歳 / 日本)
マ・ティアンクン Tiankun Ma(17歳 / 中国)
第5位 エリック・グオ Eric Guo(22歳 / カナダ)

優勝のキムさんは併せて聴衆賞、プレス審査員賞、パリの18の音楽院の2万人の学生による特別賞 ”パリ賞” も受賞し、賞金3万5千ユーロに加え、副賞として7月14日の40万人の観客が集まる“コンセール・ド・パリ”への出演権を得た。彼を含む入賞者は、モンテカルロ歌劇場等の数多くの音楽フェスティバルへ招待される。
国内コンクールであった第1回のピアノ部門の優勝は、サンソン・フランソワ。1946年からは国際コンクールとして開催され、日本人では1953年に田中希代子氏が初入賞(4位)、1959年には松浦豊明氏が初優勝し、その後も数多くの日本人が入賞し、近年では2019年に三浦謙司さんが1位、務川慧悟さんが2位、前回の2022年には亀井聖矢(まさや)さんが1位、重森光太郎さんが4位という優秀な成績をおさめられている。
 前列左から審査員:ジャン=マルク・ルイサダ氏、マルク・ラフォレ氏、酒井茜氏、野原みどり氏
前列左から審査員:ジャン=マルク・ルイサダ氏、マルク・ラフォレ氏、酒井茜氏、野原みどり氏
後列左から日本予選通過者:大山桃暖さん、高尾真菜さん、島多璃音さん、神原雅治さん、伊舟城歩生さん、稲垣慈永さん
今回は世界18か国から126名の応募者があり、(株)河合楽器製作所とのパートナーシップ協定締結によって実現した日本予選を通過した、稲垣慈永(いながき じえい)さん、伊舟城歩生(いばらき あゆむ)さん、大山桃暖(おおやま もだん)さん、神原雅治(かんばら まさはる)さん、島多璃音(しまた りいと)さん、高尾真菜(たかお まな)さん、の6名と、青島周平(あおしま しゅうへい)さん、藤澤亜里紗(ふじさわ ありさ)さん、松田彩香(まつだ あやか)さん、永康毅(ながやす たけし)さんの4名 を含む32名がパリに集まった。セミファイナルへは10名が進出し、最終日の3月30日にショパンやリストらも演奏したという国立オペラ・コミック劇場で行われたファイナルでは、5名のファイナリストがギャルド・レピュブリケーヌ管弦楽団(指揮:バスティアン・スティル) とピアノ協奏曲を協演。このオーケストラは、1848年に軍楽隊の12名の金管楽器奏者により創設され、今日では世界最高峰の吹奏楽団ともしても知られているが、今回は弦楽奏者を加えて管弦楽団として参加した。審査員には、エヴァ・ポブウォツカ氏、パーヴェル・ギリロフ氏、ミハイル・ルディ氏、マルク・ラフォレ氏といった一流音楽家をはじめとする10名が名を連ねた。
今回のファイナリスト5名は17歳が3名で、最高年齢が22歳という年齢層!(ちなみにコンクールの年齢制限は16歳~33歳)珍しく5名全員が異なる選曲をしていたので、観客はまるでコンサートのように5つの協奏曲を堪能できた。

レビュー
トップバッターは、現在名古屋音楽大学のピアノ演奏家コースで関本昌平氏、清水皇樹氏に師事されており、仙台国際音楽コンクール、ピティナ特級、ドイツのハンス・フォン・ビューロー国際コンクール等の入賞歴がある神原雅治さん。神原さんは約50分にも及ぶ大作、ブラームス《ピアノ協奏曲第一番》を選曲し、マエスト―ソ(荘厳な)と書かれた第1楽章の壮大なオーケストラの序奏を冷静に聴きながら集中し、彼がしっとりと弾き出すと、指揮者とオーケストラは彼に寄り添うように演奏。神原さんは特にエスプレッシーヴォ(表情豊かに)と書かれたメロディーを長く感じながら、非常によく歌い、アルペッジョの音色はまるでパールのような輝き。第2楽章は慰め、悲しみが混ざったような感情があふれたなんとも美しい楽章だが、まるで自分に語りかけるように弾き始める。特にカデンツァの前の弱音での緊張感には吸い込まれそうになった。3楽章の出だしは、それまでの楽章とは一転してしっかりと勢いよく弾き始め、時には夢を見るように、そして第2カデンツァからは、今までの想いを全て出し切るような感じで盛り上がり、見事に弾き終えた。
2番手は、カナダのトロント王立音楽院/グレン・グールド・スクールで学士号を取得後、現在アーティスト・ディプロマ・プログラムで、ジョン・ペリー氏とジェームズ・アナグノソン氏の下で学んいるエリック・グオさん。過去に様々な国際コンクールに入賞しているが、特に2023年にポーランドで開催された第2回ショパン国際ピリオド楽器コンクールの覇者として有名なグオさんは、ショパン《ピアノ協奏曲第2番》を選曲。彼はオーケストラの序奏を聴きながら身体を揺らして音楽に浸り、第1楽章を劇的に弾き始める。彼はピリオド楽器コンクールで優勝後、近年はフォルテピアノで演奏する機会も増えたからか、その影響を時々感じさせられる演奏。2楽章の出だしの深い音、コロコロとした音の粒、自由な即興的なパッセージはお見事。3楽章の何度も変化されて繰り返される主題を常に新鮮に表現し、特に細かい音符の速いパッセージは華麗であった。

休憩前の3番目は、17歳組の1人である 韓国のキム・セヒョンさん。彼は現在ボストンに在住し、ハーバード大学で英文学を専攻しながらニューイングランド音楽院でピアノをハエ=スン・パイク氏とダン・タイ・ソン氏に師事。これまでにアメリカで2023年に開催された若いアーティストのためのクリーヴランド国際ピアノ・コンクールで優勝し、併せて聴衆賞も受賞している。彼はラフマニノフ《ピアノ協奏曲第3番》の冒頭のユニゾンのメロディーを冷静に弾き始めたかと思うと、今度はグイグイとオーケストラを引っ張る。2楽章の慰めのようなフレージングの感じ方、軽やかなワルツ、胸が張り裂けるような表現には息を呑んだ。アタッカで始まる3楽章への繋ぎのオーケストラとの呼吸もバッチリ。第1楽章の第2主題のレント、モルト・エスプレッシヴォ(ゆっくり、非常に表情豊かに)が再現されているメロディーは思いっきり歌い、フルートとホルンとのデュエットも美しかった。彼は音色のバラエティー、幅の広いデュナーミク、17歳とは信じ難い深みのある表現で感動を与えてくれた。

4人目は、同じく17歳の韓国のイ・ヒョさん。彼は、2022年の同コンクールに於いて、亀井聖矢さんと優勝を分け合ったイ・ヒョクさんの実弟で、近年は兄弟デュオとしても活動をされている。2014年にヴァイオリンでモスクワ音楽院付属中央音楽学校へ入学し、国際コンクールで優勝できるほどのヴァイオリンの実力の持ち主でもある。2016年からピアノの勉強を再開したという彼は、14歳の時にポーランドの国際アルトゥール・ルービンシュタイン記念コンクールで第3位を受賞し、このコンテスト史上最年少の入賞者となった。イさんはプロコフィエフ《ピアノ協奏曲第3番》を選び、穏やかなクラリネットのソロで始まり、段々とオーケストラのテンポが上がってくるオーケストラの序奏の流れに乗って、勢いよく弾き始める。2楽章では彼のリズム感の良さが顕著にでており、自由自在に鍵盤を扱う姿から余裕さえ感じられた。3楽章はオーケストラと共にスピード感のある音楽をつくり、コーダの最後は、次々に打ち上げられて夜空に輝く豪華な花火のようであった。

最後は、17歳の中国のマ・ ティアンクンさん。同じパリで2023年に開催されたアニマート国際ピアノコンクール(ショパン・エディション、年齢制限:30歳)の優勝をはじめ、様々な国際ジュニアコンクールで入賞し、現在は北京の中国中央音楽院のホアン・ヤーモン氏のもとで研鑽中のマさん。彼の選択したベートーヴェン《ピアノ協奏曲第4番》は、先ずピアノソロが入り、それに応えるようにオーケストラが演奏するという作品。彼はオーケストラのチューニングが終わると、ゆっくりと手を鍵盤の上に置き、”ドルチェ”(柔らかく)でピアノと書かれた冒頭の和音を、会場にもしっかり通るきれいな音で弾き始めた。構成力があり、様々なカラーで時にはゴージャスに、カデンツァの最後の弱音でのトリルにはうっとり。2楽章も重く何かを訴えるようなオーケストラに対し、ウナ・コルダの箇所を内省的に弾きはじめた。時には祈るような音色で、トレ・コルデの箇所との性格のコントラストも付いていた。3楽章は切れの良い出だしで、彼の演奏は常に音楽的であった。
ファイナリスト5名全員は、今年の秋に開催されるショパン国際ピアノコンクールの為の予備予選出場権を得ていたという共通点があったのも興味深い。(ただし、キム・セヒョンはショパン国際ピアノコンクールと仙台国際音楽コンクールを既に辞退している。)
今年は他にも世界各地で数多くのメジャーな国際ピアノコンクールが開催され、”国際ピアノコンクール・イヤー”とも呼ばれている。
ファイナリストをはじめ、今回の出場者全員にエールを送りたい!
(ピアニスト/国際ピアノコンクール・リポーター アーリンク明美)
▼2024年11月に開催された「ロン=ティボー国際コンクール2025 日本予選」における、神原雅治さんの演奏動画
■Shigeru Kawaiフルコンサートピアノ 『SK-EX』について
「世界一のピアノづくり」を目指す当社が、2001年に発表したフルコンサートピアノのフラッグシップモデル。コンサートピアノとして要求される最高の表現力を実現するために、響板には十分に厳選した材料だけを使用し、原器工程と呼ぶ伝統的な手作り工程で生産。またShigeru Kawaiグランドピアノシリーズで採用した新素材を随所に取り入れた革新的なウルトラ・レスポンシブ・アクションIIが、高い連打性と安定したタッチ感を提供する。繊細で伸びやかなピアニッシモに加えて、力強い輪郭のはっきりした響きが特長。